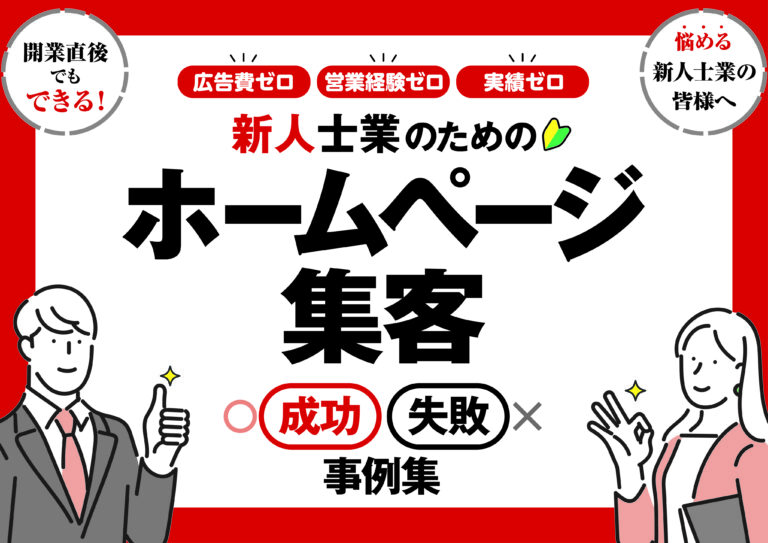1. 士業にとっての営業とホームページの位置づけ
士業の事務所経営において、集客の中心はあくまでアナログ営業です。人とのつながり、紹介、異業種交流会、セミナー登壇──こうしたリアルな場での出会いこそが、新しい案件のほとんどを生み出しています。これは税理士であっても、弁護士であっても、社労士であっても、大きな違いはありません。
つまり、士業にとって最も注力すべきはアナログ営業であり、そこをしっかりやっていれば事務所は成り立ちます。実際に多くの先生が「ホームページは作ったけど、ほとんど更新していない」「営業は紹介と人脈が中心」という状況でも、経営が問題なく回っているのが現実です。
この点を理解せずに「Web集客をしないと未来はない」と煽る制作会社もありますが、それは士業の実態を知らないからこそ言えることです。士業は他の業種のように広告を打って一気に案件を取るスタイルではなく、信頼を積み重ねて長期的に依頼を受け続けるスタイルです。だからこそ、Webが営業全体の中で果たす役割は限定的なのです。
では、その中でホームページはどんな役割を担うのか。結論から言えば、ホームページは「アナログ営業を後押しする存在」であり、同時に「補助的にWeb集客を支える存在」として意味を持ちます。決して万能ではないけれど、アナログと組み合わせることで確かな力を発揮するのです。
2. Web集客は2割という現実と、その意味
士業の営業活動を冷静に見渡すと、アナログ営業が8割、Web集客は2割程度というのが実態です。もちろん数字は正確な統計ではなく体感値ですが、多くの士業の先生が「確かにそんな感じだ」と納得されるのではないでしょうか。
この2割という数字には重要な意味があります。まず、アナログ営業が強ければ、Webをやらなくても経営は成り立ちます。実際、紹介や人脈で十分に案件が回り、ホームページは作ったまま放置している先生も少なくありません。それでも事務所が続いているのは、まさにアナログ営業が8割を支えているからです。
一方で、この「所詮2割」だからこそ、ほとんどの士業はWeb集客に真剣に取り組んでいません。つまり競争が激しくないため、もし少し本気でWebに取り組めば、その2割をしっかり獲得できる余地が残されています。放置していても問題はないけれど、やれば成果が出やすい領域──それが士業におけるWeb集客なのです。
ただし誤解してはいけないのは、この2割だけで事務所を回していくのは現実的ではないということです。営業の軸はあくまでアナログ。その土台の上に、Webの2割をどう乗せていくかが大事なのです。これが士業におけるホームページ活用の基本的な考え方になります。
3. ホームページの第一の役割はアナログ営業の加速
士業にとってホームページの役割を一言で表すなら、「アナログ営業を加速させること」です。
例えば、名刺交換をした相手、セミナーで話を聞いてくれた人、紹介で名前を知った人──こうした見込み顧客は必ずといっていいほどホームページを確認します。そのときに、単なる事務所案内が載っているだけでは「誰に頼んでも同じ」という印象になってしまいます。しかし、先生の想いや信念、これまでの歩みや専門性がしっかりと伝わるホームページであれば、見込み顧客の信頼は一気に高まります。
つまりホームページは、アナログ営業で出会った相手に「この先生にお願いしたい」と思わせる後押しをする存在です。紹介の質と量を高め、思い出してもらう頻度を増やし、アナログ営業の成果をさらに確実なものにするための装置なのです。
グットアップでは、この点をとても重視しています。Web集客という観点だけでなく、「パーソナル・ブランディング」や「ストーリーマーケティング」を意識して制作を行います。先生自身の人柄や背景をストーリーとして発信することで、共感され、覚えてもらい、必要なときに思い出してもらえるようになる。それが、士業にとって本当に価値のあるホームページだと考えています。
そして、ここにさらに「Web集客」の要素を加えることで、事務所経営の成功確度はぐっと高まります。ホームページは、アナログ営業を補強するだけでなく、検索や地域での情報収集を通じて新しい顧客と出会うきっかけにもなります。士業にとってWeb集客の比率は全体の2割程度ですが、この2割を積み上げていくことができれば、事務所の成長スピードは確実に変わっていきます。
つまり、「アナログ営業のためのホームページ」を土台としながら、「Web集客」を戦略的に取り入れていく。この二つが合わさることで、紹介もWebも増え、営業全体の力が最大化されるのです。
この考え方を踏まえ、次のセクションでは「士業の成長ステージごとに、どのようにWebを活用していくべきか」を解説していきます。
4. 事業ステージ別の士業のWeb活用
士業の事務所運営においては、開業直後から安定経営、そして事業拡大期へと、成長ステージによって直面する課題が大きく変わります。営業の中心がアナログであることに変わりはありませんが、その補完としてのWebの役割はステージごとに異なります。
つまり、どの段階にいるかによって、ホームページの作り方・投資の仕方・活用の仕方は変わっていくのです。最初から完成された集客システムを作り込む必要はなく、自分の事務所の成長に合わせてWebを育てていくことが大切です。
もちろん、ここで紹介するのはあくまで「一般的なケース」です。先生自身の資金力や事務所を構える地域性、そのときどきの流行や時代の背景によって最適解は変わってきます。しかし、大前提として士業の営業は「アナログ8割・Web2割」。まずはアナログに注力し、その行動を後押しする形でWebを組み合わせていくことが基本となります。
以下では、士業の代表的な3つの事業ステージに分けて、それぞれでどのようにWebを活用すべきかを解説します。
4-1. 開業直後の士業と地域密着Web集客
開業直後の士業にとって、営業の主軸は間違いなくアナログです。人脈づくり、名刺交換、セミナーや異業種交流会での出会い──これらが最初の案件をつくります。ホームページに大きな期待をかけるよりも、まずは自ら動いて信頼を積み重ねることが欠かせません。
一番仕事が欲しいこの時期、アナログ営業が苦手だからこそ「Webでなんとかしたい」と考える先生も多いでしょう。しかし残念ながら、新人士業がもっともWeb集客に向いていない時期でもあるのです。なぜなら、Webで成果を出すためには多くの集客ページや記事を作り込み、相応の工数と費用を投じる必要があり、資金力のある先輩士業がすでにそこに投資しているからです。
だからこそ、この時期のホームページは「顧客を直接集める道具」ではなく、「アナログ営業をブーストするための存在」として考えることが重要です。顧客を集めるのではなく、顧客を紹介してくれる人を増やすために、信頼を高めるホームページを持つ。これが開業直後に取り組むべき基本です。
そのうえでWebを使うなら「地域密着Web集客」が現実的な選択肢です。検索ユーザーの多くは「近くの専門家を探したい」と考えており、大手や都心部の事務所よりも、地元の先生を選ぶ可能性が高いのです。地域特化型であれば大きな投資をしなくても成果につながりやすく、限られた資金で始められます。
つまり、開業直後のホームページは、まず「名刺代わり」として信用を担保し、アナログ営業で出会った人に安心感を与える。そのうえで地域密着型のWeb集客を少しずつ組み合わせる。これが、開業直後の士業にとってもっとも現実的で成果につながるWeb活用です。
4-2. 開業3年目頃:紹介が増え、Webの役割が変わる時期
事務所を立ち上げて3年ほど経つと、アナログ営業が軌道に乗り、紹介からの案件が増え始めます。この時期には、今まで以上に多くの人が先生のホームページを見るようになります。ところが、開業当初に「とりあえず」で作ったホームページがそのままだと、見られること自体が恥ずかしくなってきます。「もっとしっかり自分の強みや想いを伝えたい」と考えるようになるのです。
さらに、このタイミングでは案件数が増えすぎて一人では対応できず、スタッフを雇い始めるケースも多く見られます。そうなると実務に追われ、これまでのように自分が積極的に動いてアナログ営業を行うことが難しくなります。その結果、補完としてのWebの重要性が一気に増してくるのです。
また、紹介が増えていく段階だからこそ、ホームページには「共感され、覚えてもらい、思い出してもらう」という役割が強く求められるようになります。単なる業務紹介ではなく、「この先生だからお願いしたい」と感じてもらえるストーリーや人柄を伝えることが必要になってくるのです。
つまり、開業3年目頃は「ホームページを通じて紹介の効果を最大化し、さらにWebを補完的に活用して集客を安定化させる」というフェーズに入る時期です。
4-3. 事務所拡大期:Webを丸ごと任せる段階へ
さらに事務所が成長し、売上も拡大していくと、次に直面するのは「人を増やした分だけ案件も必要になる」という課題です。スタッフを増やせば固定費は大きくなり、案件を安定的に供給する仕組みを整えなければ経営のリスクも高まります。この段階では、Web集客が事務所の成長を支えるための重要なエンジンとなります。
ただし、Web集客を本格的に回していくには、戦略設計・コンテンツ制作・記事執筆・広告運用など多岐にわたる作業が必要であり、社内でWeb専任スタッフをゼロから育てるのは簡単ではありません。むしろ、スタッフ1名分の人件費を投じて外部の専門業者に丸ごと任せた方が、確実に成果につながるケースが多いのです。
この段階に入ると、ホームページは「アナログ営業の補完」や「名刺代わり」ではなく、事務所の成長を支える中核的な営業資産になります。Webを丸ごと任せることで、先生自身は本業に集中しながら、安定的に新しい顧客を獲得できる体制が整っていくのです。
5. ホームページ制作の進め方:最初は最低限、後から育てる
ホームページ制作には大きく二つの考え方があります。ひとつは最初から大きな投資をして、ページ数も内容も充実させた完成度の高いサイトをつくる方法。もうひとつは最低限必要なものだけを整え、事務所の成長に合わせて徐々に育てていく方法です。
グットアップが推奨しているのは後者──「開業直後は最低限、その後、アナログ営業が軌道に乗ってきてからWebを本格的に育てていく」スタイルです。
なぜなら、士業の営業の基本はあくまでアナログ8割・Web2割。開業直後の士業にとっては、まずはアナログ営業で信頼を積み重ねることが最優先です。ホームページはそのアナログ営業を後押しする「名刺代わり」として最低限整っていれば十分。そこで無理に大きな投資をしても、期待通りのリターンは得られません。
一方で、事務所が成長し、紹介が増えたり、スタッフが増えて営業体制が変化したりすると、ホームページの役割も変わっていきます。このときに必要なコンテンツを追加し、Web集客を強化していくことで、自然な形でサイトを「育てる」ことができます。
目安としては、毎月5〜10万円の販促費を投資できるようになった段階で、Webコンサルティングを導入するのが最適です。私たちが伴走しながら毎月1回オンラインMTGを実施し、ホームページの現状を確認、改善点や改善策を提案します。そして次のMTGまでに実行していただく。これにより「PDCAを回す仕組み」が確立され、少しずつホームページを集客装置として成長させていけます。作業は基本的にご自身で行っていただきますが、時間的・人的に難しい部分は弊社が代行することも可能です。
さらに、毎月10〜20万円の販促費を投資できるようになった段階では、Webコンサルティングに加えて「ホームページ運用代行」をお任せいただくのがベストです。毎月1回のオンラインMTGで方向性を決め、その実行部分(ページ追加や記事制作など)はすべて弊社が代行。これにより、先生は本業に集中しながらホームページを完成形に育て上げることができます。
つまり、最初から完璧を目指すのではなく、事務所の成長に応じて投資の幅を広げ、必要な機能を加えていく。これが、士業にとってもっとも現実的で無理のないホームページ制作・運用の進め方なのです。
6. グットアップの考える士業ホームページの理想形
ここまで述べてきたように、士業にとって営業の中心はアナログであり、Webはあくまで補完的な役割です。しかし、「アナログ営業のためのホームページ」を土台にしつつ、「Web集客の仕組み」を段階的に積み上げていくことで、事務所運営の成功確度は大きく高まります。
グットアップが考える理想のホームページは、ただ案件を集めるだけのツールではありません。先生自身の人柄や想いを伝え、共感され、覚えてもらい、そして必要なときに思い出してもらう──そうしたパーソナル・ブランディングとストーリーマーケティングを軸に据えています。これによって紹介が増え、アナログ営業がさらに強化されます。
同時に、検索や地域からのWeb集客でも「この先生にお願いしたい」と思ってもらえるような差別化を実現します。競合事務所が似たようなサービスや料金を掲げるなかで、「最後に選ばれる理由」をホームページで明確に打ち出すのです。
さらに、事務所の成長ステージに応じて、ホームページを段階的に育てていくことも不可欠です。開業直後は信用を担保するための最低限のサイト。その後、紹介が増える時期には、自分の強みをよりしっかりと伝える業務特化型のサイト。そして拡大期には、戦略設計からコンテンツ運用までを一括して任せ、安定的に案件を獲得できる仕組みへ。
アナログ営業8割 × Web集客2割。この現実に即したバランスを土台にしながら、紹介もWebも同時に増やしていくこと。それがグットアップのホームページ制作の理想であり、私たちがお客様にお届けしたい価値です。